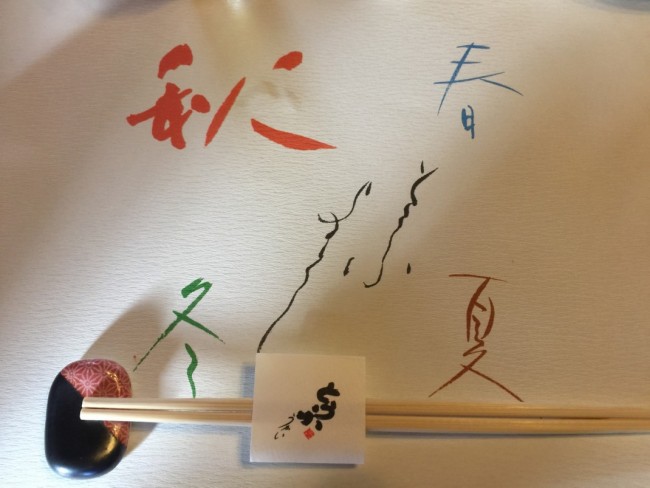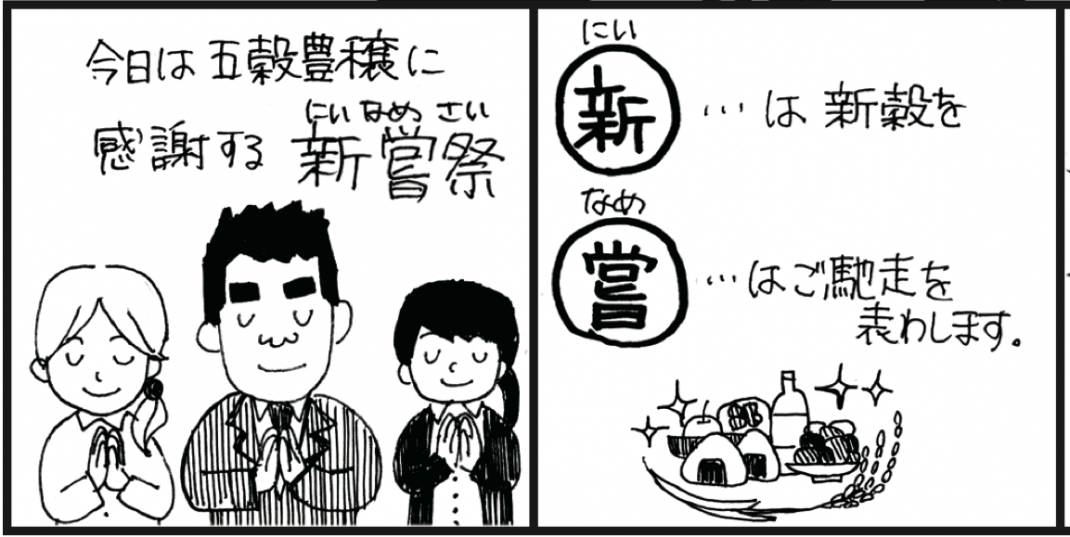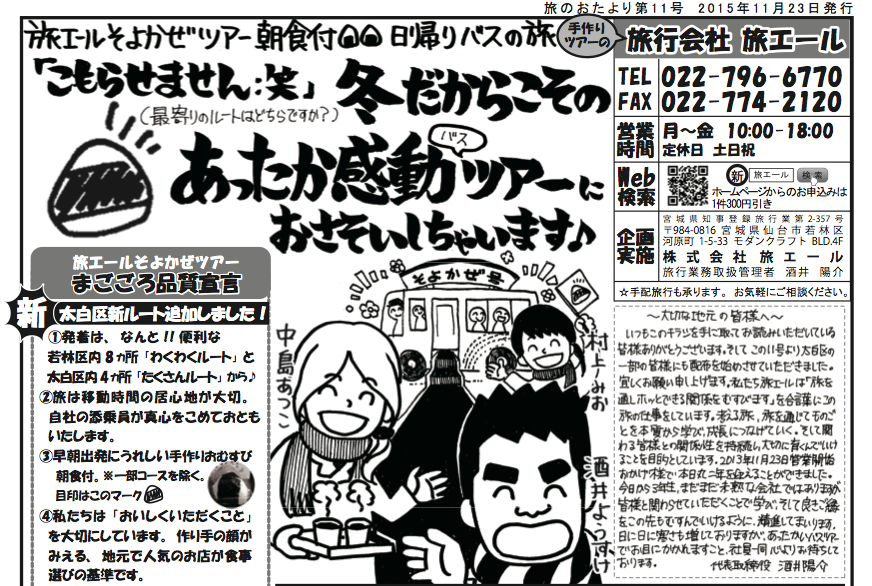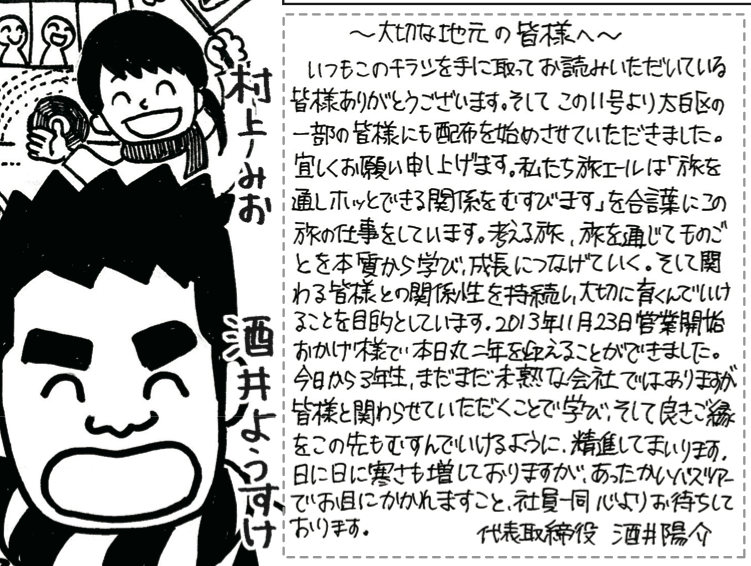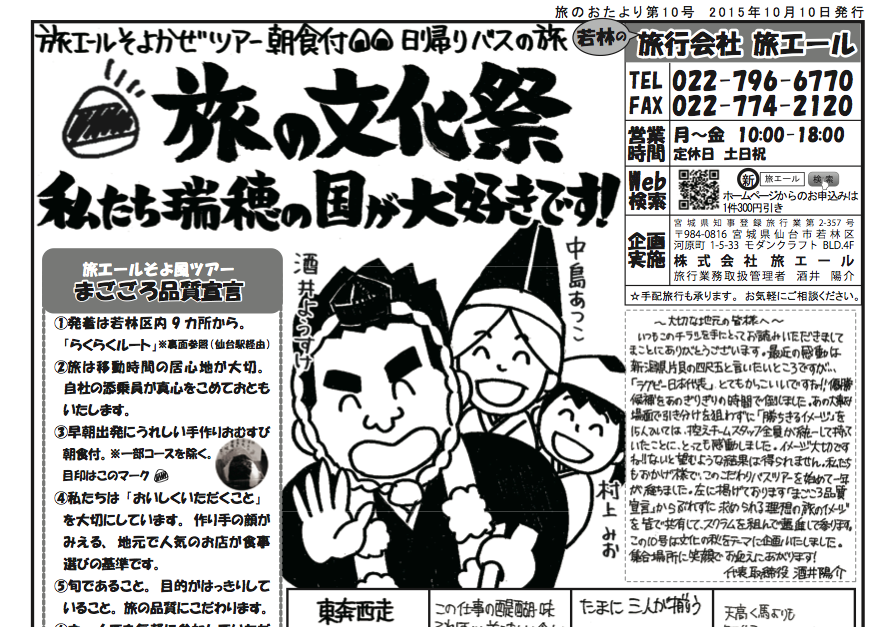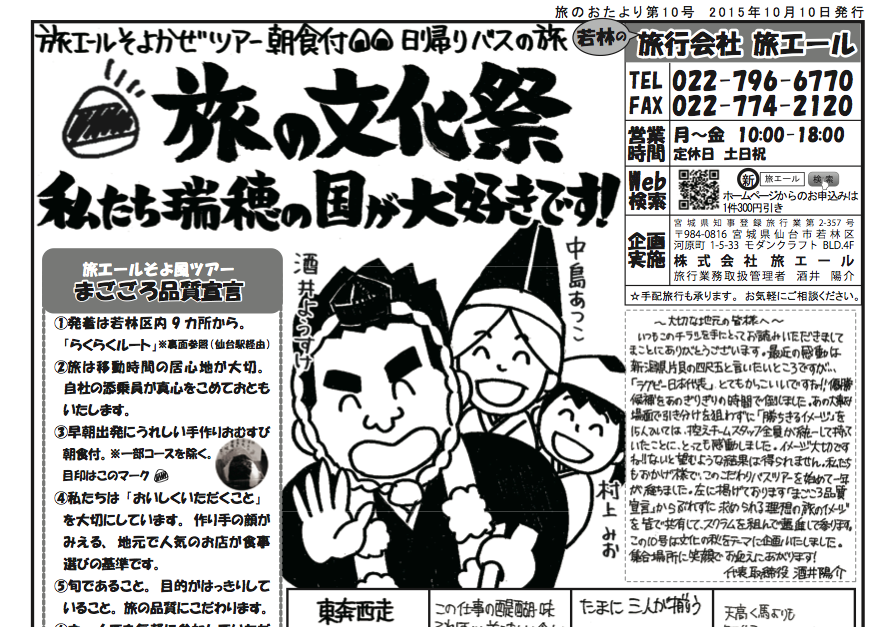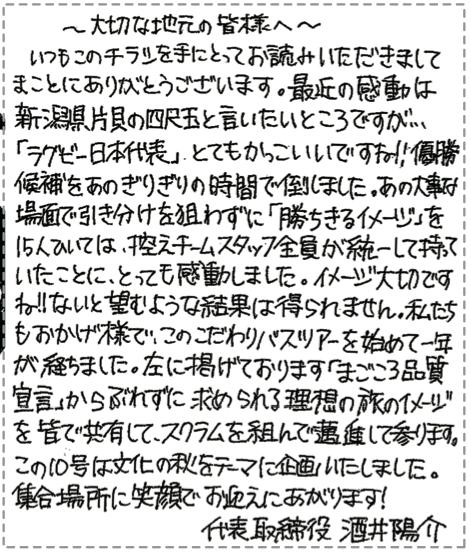あがりこ大王 も 雪化粧。
大好きなにかほ情報をお届けします。
旅エールのバスツアーのときには 必ずガイドとして同行していただく
にかほの あったかガイド 伊藤良孝 さんからのお便り
〜〜〜〜〜
雪のシーズン到来
12月からしばらくは森も眠りの入ります。
今日看板のシート掛けに行ったところ、途中から県道が積雪の状態に
変わりました。
管理棟も12月から春まで閉鎖になります。
静かな森になりますが、時々は
雪の中をトレッキングで楽しみたいと思います。
綿帽子のオウウバユリ、足跡はキツネです。
伊藤 良孝
〜〜〜〜〜
仙台 も だいぶ冷え込んできました。
ボクも今日から ハイソックスです(笑)
「首」をから熱をに逃がさないようにすると、イイそうですよ
首、手首、足首
あったこくして、これからの季節をたのしみましょうv